
所得に応じた累進課税が適用
(税率は5%~45%で変動)

起業する際は個人事業主と法人の選択があり、信用の問題だけではなく税制面や運営コストを比較することが大切です。
コストとメリット:
個人事業主と法人のどちらがお得なのか徹底比較しました。
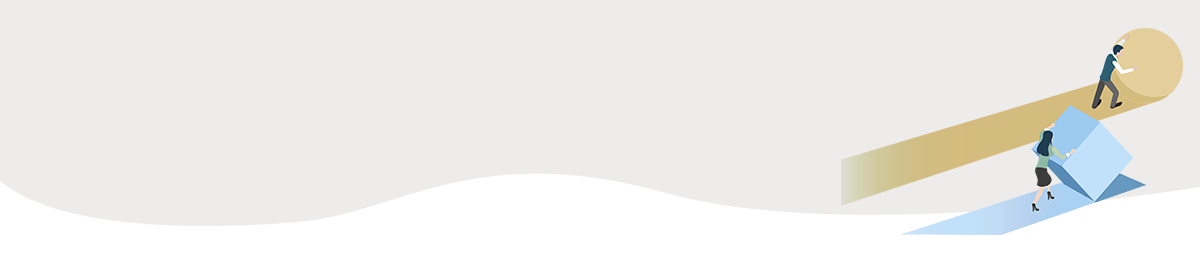
◆税率の構造と法人化の有利性

所得に応じた累進課税が適用
(税率は5%~45%で変動)
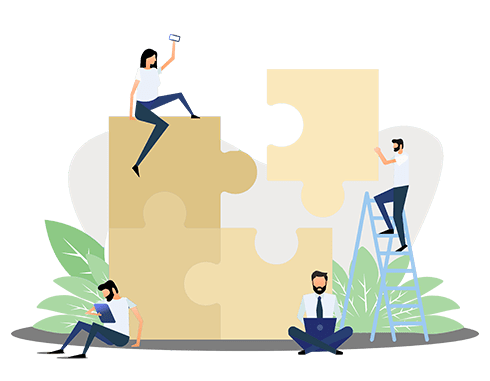
原則として23.2%(2023年改定時)の一定税率
【結論】利益が大きい場合は法人にした方が所得に対する税金が安くなってお得です。
法人は納めないといけない税金の種類が多くなるため、所得税と法人税だけを比較するのではなく、トータルで払う税金やコストで比較するようにしてください。
所得税や法人税は売上から経費などを差し引いた純利益を元に計算されます。
法人は経費計上の範囲が広く、役員報酬や福利厚生費なども経費にできるため節税の工夫がしやすいです。
個人事業主も必要経費として認められる範囲は広いですが、税務上の制約があるので注意してください。
個人事業主の場合は確定申告で事業収入の申告をする必要があります。選択肢は以下の通りです。
| 申告方法 | 特徴 | 控除額 |
|---|---|---|
| 白色申告 | 手軽にできる。 | 10万円 |
| 青色申告 | 複式簿記が必要。税務署に開業届を出しておく必要があり、帳簿の処理などが複雑。 | 最大65万円 |
青色申告のポイント:
法人の場合は様々な項目から構成される決算書を作成して税申告しないといけません。
法人の申告の難易度とコスト:
法人の方が経費計上などによる節税対策の範囲が広いですが、税務調査のリスクが高いためきっちり申告しないといけません。
◆個人事業主
個人事業主も税務調査が入ることがあるため、適切な経費計上と税申告をする必要がありますが、実際のところは年商1,000万円以下の個人事業主に本格的な税務調査が入ることは滅多にありません。
経営者の実態として、年商1,000万円以下のうちは個人事業主を選択して、年商1,000万円を超えたら税務調査や追徴課税のリスクを懸念して法人化を検討するケースが多いです。
税負担の調整方法:
利益が出ている場合は、税理士などと相談しながら節税対策の方法を考えてください。
個人事業主の場合も税理士に相談したうえで、法人化するべきかの判断や節税の方法を検討するとよいでしょう。

法人の場合:
個人事業主の場合:
法人は維持コストが高いですが、信用を得られるので顧客や金融機関から信頼されやすく、社会保険に加入するのは福利厚生の充実になります。
◆まとめ
法人・個人それぞれの維持コストを比較し、費用だけではなくメリット・デメリットをしっかり理解して判断することが大切です。
つまり、法人と個人でどちらがお得なのか決まった答えはありません。
一般的には売上と利益が大きくなるほど法人の方がお得ですが、例外もあります。
税理士などの専門家に相談しながら、慎重に検討するとよいでしょう。